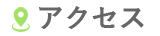国立極地研究所 更新情報一覧
- 2026.02.19
- 遠くアラスカ・カナダの陸地からやってきた胞子が北極海上で雲の種として働く? ―電子顕微鏡によるエアロゾル粒子の詳細解析から―
- 2026.02.03
- 南極観測70周年記念特設サイトを公開しました
- 2025.12.22
- 極地研サイエンスカフェ「もっと知りたい!北極!~地球のようすをみてみよう~」開催します!(3月26日、小学校5年生と6年生対象)
- 2025.12.22
- イッカクが水中録音機器に接触することを発見~係留系の安全性に疑問を提起~
- 2025.12.22
- Starlink活用による南極からの3D点群データと映像のリアルタイム伝送に成功~極地・遠隔地の作業DX実現に向けて~
- 2025.12.11
- 過去の南極氷床の急激な薄化と再厚化~現地調査と衛星観測、モデル研究の統合により、地域固有の氷床の変動が明らかに~
- 2025.11.27
- 極域電離圏の“宇宙天気図”を描く新技術 — 観測とAIモデルの融合で宇宙環境を再現 —
- 2025.11.18
- 2025年9月、北極海の海氷域面積が年間最小を、南極海の海氷面積が年間最大を記録
- 2025.11.11
- 南極氷床の融解がさらなる融解を呼ぶー将来、南極で起こりうる連鎖的氷床融解を提唱ー
- 2025.11.06
- ベリリウム7(⁷Be)が明らかにした南極域の大気の流れ
- 2025.11.06
- 極地研サイエンスカフェ「昭和基地の仕事と生活」を開催します!(2月4日開催)
- 2025.11.06
- 地球に降り込む高エネルギー電子を地磁気による磁気ミラー力が跳ね返す効果を観測的に実証
- 2025.11.05
- 南極ドームふじ氷床コア深部の多結晶構造を精緻に解明
- 2025.10.29
- 大規模火山噴火と夜光雲の関係についての世界初観測に成功
- 2025.10.20
- 中央北極海のメルトポンドの栄養塩動態を解明~海氷栄養塩循環におけるメルトポンドの重要性を提示~
- 2025.09.11
- 小惑星リュウグウの岩石は氷を十億年も持っていた! ―地球の材料天体に従来見積もりの2~3倍の水があった可能性―
- 2025.08.22
- 清浄な南極地域でもヘイズ現象が出現 大気化学過程・雲過程を介して気候変動に与える影響も
- 2025.08.22
- 秋季太平洋側北極海の海氷変動がマイクロプランクトン群集を変えることを解明
- 2025.08.22
- アジア地域初!陸域生態系によるCO2吸収動態を明らかにする大規模基盤データセット「JapanFlux2024」を構築
- 2025.08.07
- 南極内陸域で世界平均より早い気温上昇を初観測~南インド洋の温暖化が南極の氷を溶かす~
- 2025.08.07
- リュウグウに残された“衝撃の痕跡”を再現!― 実験で迫る原始太陽系小天体の衝突の記憶 ―
- 2025.07.07
- アジア低緯度域からの放出増加により大気メタン濃度が急上昇(2020–2022年)
- 2025.07.04
- 全球海洋モデルにより福島第一原発から放出されるトリチウムの濃度分布を予測
- 2025.07.04
- 南極リュツォ・ホルム湾およびトッテン氷河沖で自律型海中ロボットによる無索での海氷下航行に成功
- 2025.06.25
- MegaMove:バイオロギングで大型海洋動物111種を追跡調査
- 2025.06.24
- 南大洋上は–25℃の低温環境でも水雲が多い~日射を強く反射し熱収支を左右~
- 2025.06.05
- 井上崚特任研究員が「2024年度日本雪氷学会関東・中部・西日本支部賞(論文賞)」を受賞しました
- 2025.04.18
- 北極の冬季海氷域面積が衛星観測史上最小を記録
- 2025.04.17
- IUGONETプロジェクトメンバーが科学技術分野の文部科学大臣表彰「研究支援賞」を受賞
- 2025.04.16
- 藤井良一 特任教授がJpGUフェローに選ばれました
- 2025.04.07
- 南極海の海洋環境と生態系の長期変化を解明 大規模な生態系総合調査により南極海東インド洋区の長期変化が明らかに
- 2025.04.07
- 北極域研究強化プロジェクト(ArCS III)がスタートしました
- 2025.04.02
- 偏西風強化が東南極氷床への海洋熱輸送の増加をもたらす~地球温暖化が南極氷床の融解を促進するメカニズム~
- 2025.03.31
- 国立極地研究所一般公開を2025年9月27日(土)に開催します
- 2025.03.31
- 南極・北極科学館の累計来館者数が40万人を超えました!
- 2025.03.03
- カナダの山火事で北極海の雲の性質が変化~大気の川が山火事由来のエアロゾル粒子を北極海へ輸送~
- 2025.03.03
- あべ俊子文部科学大臣が国立極地研究所を視察
- 2025.02.06
- 氷河の流動加速を引き起こす、融け水、雨、潮の満ち引き~グリーンランドで氷河流動変化のメカニズムを解明~
- 2025.02.04
- サイエンストーク「北極海氷予報の最前線」を開催します!(3月22日、高校生以上)
- 2025.01.30
- シベリア森林火災が遠く離れた洋上の雲のもととなる?―氷晶核濃度とエアロゾル成分濃度の比較から―
- 2025.01.23
- ドローンによる気象観測の国際プロジェクトに参加~社会実装に向けた試み~
- 2025.01.22
- グリーンランドのアイスコアから過去350年間のブラックカーボンの濃度と粒径を高精度で分析
- 2025.01.15
- 南極隕石ラボラトリー「南極隕石コレクション」が国際地質科学連合の「IUGS Geo-collection」に認定
- 2025.01.07
- SHRIMP共同利用申請募集開始しました(2025年度第1四半期)期間:01月01日~02月15日
- 2024.12.25
- スーパープレッシャー気球とPANSYレーダーによる近慣性周期重力波の同時観測に成功
- 2024.11.19
- 磁気嵐起源の「下から上」へ伝わった地球大気最上部の変動を発見
- 2024.11.19
- スーパープレッシャー気球による南極域の大気重力波観測計画
- 2024.11.06
- 2024年5月に日本に現れたオーロラの色の謎を解明~日本全国から寄せられた写真を解析~
- 2024.10.17
- 第4回ArCS II公開講演会『つながってる!?わたしと北極』を開催します
- 2024.10.11
- 11月20日~1月18日、企画展示「変わりゆく永久凍土の世界」を開催します
- 2024.10.11
- 北極域での気温上昇によって氷晶形成にかかわるエアロゾルは増加する
- 2024.09.30
- 脈動オーロラの形状と宇宙から降り注ぐ電子のエネルギーの関係を解き明かす観測に成功
- 2024.09.24
- 北極海の海氷域面積が2024年9月13日に年間最小値を記録
- 2024.09.02
- 前例のない多地点観測によって、南極氷床内陸における広域の積雪粒径分布を明らかに
- 2024.08.21
- 南極隕石447個を新たに分類、352個を再分類しデータを更新
- 2024.08.07
- 内藤靖彦名誉教授が第23回山階芳麿賞を受賞しました
- 2024.08.01
- 氷河融解水の流入がフィヨルドの生物生産に与える影響を評価
- 2024.07.08
- 国立極地研究所一般公開「極地研探検2024」を9月28日(土)に開催します
- 2024.06.24
- 北海道から目撃された異常に明るいオーロラの成因
- 2024.06.24
- 太陽から降りそそぐ「電子の雨」がつくりだした巨大オーロラの観測に成功
- 2024.05.20
- 北極観測センター 近藤豊 特任教授と小池真 東大准教授の著書「雲の物理とエアロゾル」が出版されました
- 2024.05.14
- 盛山正仁文部科学大臣が国立極地研究所を視察
- 2024.05.13
- アラスカ山岳氷河末端からのメタン放出をはじめて検出 ―未解明の放出源に関する新知見―
- 2024.04.19
- 同位体モデルと精密観測によりメタンの「足あと」を辿ることが可能に
- 2024.04.10
- サイエンストーク&ボードゲーム体験会「北極ってどんなところ?」を開催します!(4月27日、中学生~大人対象)
- 2024.04.10
- こどもワークショップ「どうなる? これからの北極~海氷編~」を開催します!(5月11日、小学4~6年生対象)
- 2024.03.29
- 渡り鳥による抗生物質耐性菌の南極への拡散が明らかに
- 2024.03.25
- ウェブマガジン「極」を創刊しました
- 2024.03.22
- 1,000キロの南極冬季海氷域を伝搬した波浪の観測に成功
- 2024.03.18
- ヒトの目には見えないオーロラを初撮像
- 2024.02.21
- 文部科学省情報ひろば企画展示「南極・北極から観つめる地球環境 ~南極地域観測第X期6か年計画と北極域研究加速プロジェクト(ArCS II)~」
- 2024.02.16
- 太陽風の観測値からオーロラの広がりや電流の強さを瞬時に予測可能なエミュレータSMRAI2(サムライ2)を開発
- 2024.02.01
- 国立極地研究所と国立登山研修所が包括連携協定を締結
- 2023.12.28
- アデリーペンギンが互いに行動を調節しながら群れを維持する様子を明らかに
- 2023.12.28
- 長期観測から明らかになった南極の氷河湖決壊
- 2023.11.27
- 世界で初めて南極棚氷下の大規模地層掘削を実施 西南極ロス海棚氷下での地層掘削計画(SWAIS2C)の開始について
- 2023.11.09
- 第3回ArCS II公開講演会『海から見た北極~若手研究者と学生が語る~』を開催します
- 2023.11.02
- グリーンランド氷床南東部高地の夏季融解量の増加を復元
- 2023.11.02
- 極地研サイエンスカフェ「日本の観測船による北極海上での気象観測」を開催します!(11月22日開催)
- 2023.09.19
- ヘリコプターを用いた東南極域の大規模海洋観測に初成功
- 2023.09.07
- 9月30日は極地研を楽しもう!国立極地研究所創立50周年記念特別公開『極地研探検2023』
- 2023.08.23
- 東南極最大級の氷河へ向かう暖かい海水のルートを解明
- 2023.08.17
- 磁場が地球に降り込む宇宙放射線を跳ね返す
- 2023.06.26
- 北極ツンドラに生息する土壌微生物多様性のメカニズムを解明
- 2023.06.09
- さくらサイエンス・科学技術関係者招へいプログラムによりアフリカ諸国の視察団が来所しました
- 2023.06.07
- 2023年度日本雪氷学会賞受賞 猿谷友孝特任研究員(平田賞)総研大極域科学コース井上崚さん(論文賞)
- 2023.06.07
- 南極で海氷大流出の観測に成功 ―昭和基地のあるリュツォ・ホルム湾定着氷の崩壊機構解明にむけて―
- 2023.05.19
- 南極隕石などの研究で得られる木星の形成プロセスに関する重要なヒント
- 2023.05.18
- 天文学的要因が左右する更新世前期の地球の気候と氷床量変動
- 2023.05.08
- 日本の古典籍中の「赤気」(オーロラ)の記載から発見された宇宙変動パターンの周期性と人々の反応に関する記述
- 2023.05.08
- 北極域から放出されるダストが北極下層雲での氷晶形成において重要な役割を果たすことを発見
- 2023.05.08
- 大気中の黒色炭素(すす)の光学的物性を解明
- 2023.05.08
- 極域でサメ、エイ類の多様性が乏しい理由を解明
- 2023.05.08
- 小惑星リュウグウ粒子の微小断層から読み解く天体衝突
- 2023.04.24
- 温暖化環境下において東南極氷床が融解し得ることを発見 ~海面が将来大幅に上昇するリスクへの警鐘~
- 2023.04.05
- 第19回南極設営シンポジウム 開催のご案内と発表者募集のご案内
- 2023.03.30
- 100年以上前に埼玉県越谷市に落下した隕石の分類を確定 「越谷隕石」として国際隕石学会に登録されました
- 2023.03.24
- 小惑星リュウグウの活発な地質活動の歴史が明らかに
- 2023.02.28
- 南極内陸の積雪は過去5000年間で長期的に減少し、産業革命期から顕著に増加
- 2023.02.16
- 南極の藻類が赤外線で光合成する仕組みを解明 地球外生命の新たな鍵?
- 2023.02.14
- 南極隕石が明らかにした月の火山活動の変化
- 2023.02.07
- 第2回ArCS II公開講演会『北極先住民が語る暮らしと文化 ―地球温暖化の時代に生きる―』を開催します
- 2023.02.07
- 南極生まれのペンギン「ピングー」、国立極地研究所創立50周年記念特別アンバサダー就任!
- 2023.01.17
- 極地研サイエンスカフェ「南極氷床を融かす海」を開催します!(2月14日開催)
- 2023.01.04
- 磁気嵐の発生メカニズムと大気シミュレーションから多数の低軌道衛星が喪失に至った原因を解明
- 2022.12.26
- 小惑星が生命の星・地球を創り出した リュウグウ試料の分析により、地球がどのようにして水を得たのかが明らかに
- 2022.12.19
- 世界初、南極からの8K映像のリアルタイム伝送に成功 ~観測隊の生活環境向上や情報発信強化を目指して~
- 2022.12.12
- 二次宇宙線計測データの気温効果と積雪効果を補正する新手法を開発
- 2022.12.05
- 国立極地研究所創立50周年記念特設サイトを公開しました
- 2022.12.05
- 南極・昭和基地の宇宙線計が捉えた2021年11月の宇宙線減少
- 2022.11.30
- 地域的な海水準上昇が氷床融解を促進していた可能性を提唱 -東南極氷床大規模融解に新メカニズム-
- 2022.11.16
- 超軽量風速計でドローンによる風速計測を実現 ~安全飛行と気象観測に貢献~
- 2022.11.01
- 全海洋の深層に広がる南極底層水の起源水形成機構を発見 ~海中深く大量に生成される海氷が海洋大循環を駆動~
- 2022.11.01
- 過去30年にわたる観測データから南極ドームふじ地域の詳細な基盤地形を解明
- 2022.10.21
- 氷結晶の主軸方位分布を深さ2400mにわたり詳細に分析 〜南極ドームふじアイスコアで計測~
- 2022.10.14
- 孤立陽子オーロラの直下で生じる中間圏オゾン量の極端な減少を発見!
- 2022.09.27
- 石輪健樹助教が日本地質学会小澤儀明賞を受賞
- 2022.09.27
- 石輪健樹助教が日本第四紀学会若手学術賞を受賞
- 2022.09.08
- コンピュータトモグラフィにより脈動オーロラの3次元構造の復元に成功!
- 2022.08.25
- 南極昭和基地大型大気レーダー観測で豪州の低気圧予報が改善 〜環境負荷を低減した天気予報の精度向上の可能性〜
- 2022.08.25
- 北極海の海氷減少の真相に迫る! ―北極点、海氷直下の熱の動きを徹底的に調査―
- 2022.08.23
- 小惑星探査機「はやぶさ2」Phase-2キュレーション「Nature Astronomy」に論文掲載
- 2022.07.11
- 南極海の表層にたまった熱が氷河を底から融かす~海氷の生成を遅らせて深層大循環に影響する可能性も~
- 2022.07.11
- 超高層大気分野のデータ駆動型科学を支えるウェブサービス「IUGONET Type-A」
- 2022.07.04
- 「極地研サイエンスカフェ」開催!(8月2日、小学5年生~中学3年生対象)
- 2022.07.04
- 「南極・北極サイエンスウィーク 極地研探検2022」を開催することが決まりました!~特設サイト公開~
- 2022.06.20
- 羽田裕貴・元極地研特任研究員らの論文がPEPS誌 “The Most Downloaded Paper Awards 2022” を受賞しました
- 2022.06.14
- ヒゲは水流センサー ~深海での餌採りに利用、キタゾウアザラシで初確認~
- 2022.06.14
- 静かなオーロラが地球大気を深くまで電離させる
―最先端の観測とシミュレーションで見えた宇宙と大気のつながり― - 2022.05.30
- 海洋深層大循環に激変の兆しを検出 ~低密度化により南極大陸縁辺の沈めぬ冷水が大量に中深層へ~
- 2022.05.20
- 元国立極地研究所客員教授Asgeir Brekke博士(ノルウェー)が旭日中綬章を受章されることが決定しました
- 2022.05.20
- 片岡龍峰准教授による書籍『Extreme Space Weather』が出版されました
- 2022.05.20
- 「第18回南極設営シンポジウム」開催のご案内
- 2022.05.20
- 南極域の海氷面積が観測史上最小を記録
- 2022.05.20
- 一瞬だけ光るオーロラから宇宙のコーラス電磁波の発生域における周波数特性を解明
- 2022.04.13
- 南部マリアナトラフの上部マントル比抵抗構造を解明
- 2022.04.13
- 20世紀中頃の北極寒冷化は人間活動による大気中の微粒子の増大と気候の自然変動が複合的に影響
- 2022.03.30
- 国連海洋法条約でペンギンを守る!〜国の管轄を超えた海洋生物多様性保護の必要性を科学的に証明~
- 2022.03.18
- 阿部彩子客員教授が日本学士院賞を受賞
- 2022.03.03
- 南極域で初! 昭和基地でローカル5G実証実験を実施
- 2022.03.03
- 国立極地研究所が参画している統計エキスパート人材育成コンソーシアムのホームページ公開
- 2022.03.03
- 南極・昭和基地と北極・ニーオルスンに設置した WEBカメラ映像を公開
- 2022.03.03
- 南極地域観測第Ⅹ期6か年計画で実施する一般研究観測・萌芽研究観測を募集【2023年(65次)活動開始分】
- 2022.02.18
- 菅沼悠介准教授が地球環境史学会貢献賞を、大藪幾美特任研究員が同奨励賞を受賞
- 2022.02.18
- 第18回南極設営シンポジウム開催のご案内と発表者募集のご案内
- 2022.02.17
- 第7回国際北極研究シンポジウム(ISAR-7)開催のお知らせ(2023年3月)
- 2022.02.10
- 北極域のブラックカーボン濃度測定の標準化に成功—北極温暖化に与える影響を高精度で推定可能に—
- 2022.02.02
- 国立極地研究所における新型コロナウイルス感染症罹患者の発生について
- 2022.01.31
- 国立極地研究所における新型コロナウイルス感染症罹患者の発生について
- 2022.01.26
- 安価なドローンで高精度気象観測を実現~極域の持続可能な観測網の構築へ向けて~
- 2022.01.11
- 西山尚典助教が地球電磁気・地球惑星圏学会の大林奨励賞を受賞
- 2022.01.04
- アザラシによる観測で秋~冬の南極沿岸の海洋環境が明らかに
- 2021.12.20
- 「極地研サイエンスカフェ」開催!(1/22)
- 2021.12.20
- 中国から排出されるブラックカーボンの主要起源は「家庭」~COVID-19パンデミック期の観測データ解析から
- 2021.12.20
- 海洋由来のエアロゾル粒子が南極海上空の雲の性質に影響〜衛星観測をもとに解明〜
- 2021.12.20
- 氷期の南極の硫酸エアロゾルはどこから飛来したのか?~南米アタカマ砂漠からの寄与~
- 2021.11.25
- 氷に閉じ込められた太古の大気からアルゴンの検出に成功
~過去の地球環境変動の精密解析への貢献に期待~ - 2021.11.25
- 北極海の海氷減少で雲の性質が変化
~強風による波しぶきにより氷雲の割合が増加~ - 2021.11.05
- 森林火災が北極大気を加熱する黒色炭素粒子の重要な発生源であることを実証
~北極温暖化の将来予測に貢献~ - 2021.10.27
- 「極地研サイエンスカフェ」開催!(12/4)
- 2021.10.27
- 巨大な海洋渦が暖かい海水を南極大陸方向へ運ぶ 東南極トッテン氷河を下から融かす主要な熱源
- 2021.10.27
- 札幌の積雪中に存在する光吸収性粒子が融雪に与える影響を国内・国外由来に分離して推定しました
- 2021.10.21
- 南極の湖から新種のレジオネラ属菌の単離培養に成功 本属としては初の低温耐性菌
- 2021.10.21
- 2022年度教員南極派遣プログラム派遣教員募集
- 2021.10.05
- 田村岳史准教授が日本気象学会の2021年度堀内賞受賞者に決定
- 2021.10.05
- グリーンランド氷床に飛来するダストの起源 ~アイスコア中の微量なダストから過去100年の変化が明らかに~
- 2021.09.16
- 第12回極域科学シンポジウム(2021年11月15日~11月18日オンライン開催)
- 2021.09.16
- 東南極リュツォ・ホルム湾沿岸でのGNSS観測と地殻変動の検出
- 2021.09.16
- オーロラ帯の過去3000年間の変化を再現
- 2021.08.26
- 南大洋の温暖化が引き起こした氷期における大西洋深層循環の急激な変化
- 2021.08.26
- 東南極氷床の拡大は従来説よりも早かった~最終氷期の氷床変動メカニズムの解明へ~
- 2021.09.07
- GIGAスクール特別講座 ~南極は地球環境を見守るセンサーだ!~ 9月7日(火)開催!
- 2021.08.21
- 極地研究所 一般公開~極地研探検2021~ 8月21日(土)オンラインで開催!!
- 2021.08.18~19
- 令和3年度「こども霞が関見学デー」8月18日(水)19日(木)開催!
- 2021.07.28
- 国立極地研究所における新型コロナウイルス感染症罹患者の発生について
- 2021.07.14
- 明滅オーロラとともに起こるオゾン破壊~宇宙からの高エネルギー電子が大気に及ぼす影響を実証~
- 2021.07.13
- 海鳥の目線で海洋ゴミの分布とアホウドリへの影響を調査~採餌海域内にゴミ、誤食を懸念~
- 2021.07.13
- フラッシュオーロラの形状変化の原因を数値計算で解明
- 2021.06.18
- 「はやぶさ2」サンプルカプセル内の粒子のSPring-8での分析開始について
- 2021.06.18
- 最終氷期の南極大陸の気温低下と氷床高度の見積もりを刷新
- 2021.06.18
- 第3回北極科学大臣会合(ASM3)、アジア初となる日本・東京で開催
- 2021.05.17
- 太るのも楽じゃない 毎日20時間以上を深海での餌採りに費やすキタゾウアザラシ
- 2021.05.17
- 微小な骨を持つゴカイの新種「スナツブオフェリア」余市町の砂浜で発見!骨片の獲得と進化の謎に迫る
- 2021.05.14
- 汎世界的ミューオン観測網のデータからコロナ質量放出の地球到達時の構造を解明
- 2021.05.13
- オンライン開催! 「第17回南極設営シンポジウム」開催のご案内
- 2021.05.06
- SO2排出削減にもかかわらず硫酸エアロゾル減少が鈍化する要因を特定に
- 2021.04.30
- ひとつひとつの観測データが気象予測に与える影響を簡易に評価可能に
- 2021.04.28
- 国立極地研究所における新型コロナウイルス感染症罹患者の発生について
- 2021.04.21
- 南極大陸の海岸の砂の中から新種のセンチュウを発見
- 2021.04.12
- 背中に乗った「一寸法師」 矮雄(わいゆう)をもつウロコムシの新種を発見
- 2021.03.25
- 太陽系最古の火山岩を発見!
- 2021.03.21
- 南極地域観測隊帰国報告会 オンライン開催決定!(3/21)
- 2021.03.09
- タスマン海の水温上昇が南極半島の異常高温を引き起こす
- 2021.03.02
- 消滅核種ニオブ92の太陽系初生存在度の決定-隕石の微小鉱物が記録する太陽系形成前後の元素・物質進化-
- 2021.02.25
- 未確認の多様なレジオネラ属菌が南極の湖にも生息 基地で検出の種は人間が持ち込んだ可能性も
- 2021.02.02
- 「チバニアン」の提案申請書が論文誌のウェブサイトで公開されました
- 2021.01.28
- 渡りのスケジュールは台風次第 ~エリグロアジサシのバイオロギング研究
- 2021.01.27
- 北極海の結氷予測は「雲」がカギ 「みらい」北極海航海データを利用した、数値予報モデルの検証プロジェクトから
- 2020.12.21
- 南極海で新種の多毛類を発見し、研究船「白鳳丸」からFlabelligena hakuhoaeと命名
- 2020.12.02
- 太平洋側北極海の昇温と結氷遅延メカニズムの一端を解明
- 2020.11.17
- バイカルアザラシのユニークな生態:わずか0.1グラムの小さな獲物を1匹ずつ食べていた
- 2020.11.16~12.18
- 第11回極域科学シンポジウム(オンライン開催)
- 2020.11.13
- 「習志野隕石」が国際隕石学会に登録されました
- 2020.11.13
- 貴重な南極隕石を微量で同定する新手法を開発
- 2020.11.12
- オーロラの明滅とともに、宇宙からキラー電子が降ってくる
- 2020.11.10
- CMグループに属する最も始原的な隕石の発見 ~はやぶさ2をはじめとする太陽系形成の研究に貢献~
- 2020.11.06
- 大気レーダーの観測データから大気乱流を正確に導出する手法を開発
- 2020.10.27
- 南極海海氷域における窒素固定の発見-窒素固定が全球プロセスであることが明らかに-
- 2020.10.18
- 南極北極ジュニアフォーラム2020(オンライン開催)
- 2020.10.06
- 日本初の大型北極研究プロジェクト「GRENE北極気候変動研究事業」を振り返るレビュー論文が出版されました
- 2020.10.01
- 南極移動基地ユニットが2020年度グッドデザイン賞およびグッドデザイン・ベスト100を受賞
- 2020.09.30
- ハリケーンや台風の進路予報の精度向上に北極海での気象観測強化が有効
- 2020.09.30
- 川村賢二准教授、阿部彩子客員教授、大畑哲夫元特任教授が「2020年度日本雪氷学会賞」を受賞
- 2020.09.23
- 北極海の海氷面積が9月13日に年間最小値を記録 ~衛星観測史上2番目の小ささ~
- 2020.09.18
- 南極現地調査で明らかになった過去の急激な南極氷床の融解とそのメカニズム
- 2020.09.13
- 「難局物語2020」 南極・昭和基地から等々力陸上競技場に向けて中継
- 2020.09.04
- 「電子の豪雨」現象の原因を解明
- 2020.09.02
- 「チバニアン」の地層から明らかになった直近の地磁気逆転の全体
- 2020.08.24
- 暖かい海水が白瀬氷河を底面から融かすプロセスを解明 ~海洋観測と数値モデル,測地・雪氷学分野との融合研究~
- 2020.08.04
- 北極域研究加速プロジェクト(ArCS II)のホームページを公開
- 2020.07.16
- 菅沼悠介准教授の著作「地磁気逆転と『チバニアン』」が講談社科学出版賞を受賞
- 2020.07.06
- 総研大極域科学専攻の川又基人さんが「笹川科学研究奨励賞」を受賞
- 2020.07.06
- 中国からのブラックカーボンの排出量が過去10年で約40%減少
- 2020.06.25
- 南極の海氷がペンギンの繁殖に影響するメカニズムを解明
- 2020.06.17
- 北極域研究加速プロジェクト(ArCS II)がスタートしました
- 2020.06.12
- 期間限定オンライン情報発信企画「おうちで極地」オープンしました
- 2020.06.10
- 南極・昭和基地からのライブ配信決定!
- 2020.05.28
- 大藪幾美特任研究員と総研大の繁山航さんが日本雪氷学会の支部賞を受賞
- 2020.04.22
- 佐藤 夏雄 名誉教授(国立極地研究所元副所長・現特別客員研究員)がJpGUフェローに選ばれました
- 2020.04.17
- 榎本浩之副所長が国際北極科学委員会の副委員長に就任
- 2020.04.16
- 南極海の二酸化炭素吸収:微細藻類の量だけでなく種類が鍵となる-優占群集の違いが夏期の炭素収支を左右していた-
- 2020.04.15
- 南極の湖沼周辺に生息する微生物の群集構造を解明
- 2020.03.30
- 南極隕石559個を新たに分類し、公表しました
- 2020.03.30
- ペンギン・アザラシの行動追跡から保全の重要度が高い海域を特定 -南極海の生態系保全の推進へ向けて-
- 2020.03.16
- 日本最古の天文記録は『日本書紀』に記された扇形オーロラだった
- 2020.03.10
- 氷期最寒期のダスト飛来量を複数の南極アイスコアから復元 -ダスト起源のパタゴニアからの輸送距離の違いを反映
- 2020.03.05
- 宇宙の電磁波の「さえずり」がオーロラの「またたき」を制御 - 北極域での高速オーロラ観測と科学衛星「あらせ」による国際協調観測
- 2020.02.28
- 『これからの日本の北極政策の展望』を刊行
- 2020.02.28
- 過酷な自然環境におけるリスクマネジメントの実践知の解明 -南極地域観測隊で史上初! 「人文社会科学」分野での共同研究で成果を発表
- 2020.02.20
- 第16回中高生南極北極科学コンテスト入賞提案集を公開
- 2020.02.07
- 片岡龍峰准教授が、Earth, Planets and Space誌の「EPS Highlighted papers 2019」を受賞
- 2020.02.06
- 東京お台場の海から新種のゴカイ発見! “海の掃除屋”として生態系の維持に貢献
- 2020.01.17
- 地層「千葉セクション」のIUGS(国際地質科学連合)における審査結果について
- 2019.12.26
- 国際宇宙ステーション「きぼう」搭載の船外実験装置SEDA-AP、MAXI、CALETの連携により「電子の集中豪雨」による被ばく線量を測定-将来の宇宙天気予報に向けた基礎データを取得
- 2019.12.25
- 公的研究費の不正使用について
- 2019.12.03-05
- 第10回極域科学シンポジウム
- 2019.12.02
- オーロラを発生させる高エネルギー電子が大気圏に降り注ぐ仕組みを解明 -成層圏オゾンの破壊を誘発する原因の謎解きが一歩前進
- 2019.11.29
- お知らせ 地層「千葉セクション」の審査状況について -GSSP認定へ向けて(2019年11月)
- 2019.11.29
- 気候変動予測に貢献、「千葉セクション」の有孔虫化石 -約80万年前の海洋環境の変遷が明らかに
- 2019.11.28
- 南極大気の精密観測 -南極域初の非干渉性散乱レーダー観測を支える適応的信号処理技術を開発
- 2019.11.21
- 南極観測のサイト内に「観測隊の活動」ページを公開!
- 2019.11.07
- 太陽放射線被ばく警報システム(WASAVIES)の開発に成功 -ICAOグローバル宇宙天気センターの一員としてデータ提供開始
- 2019.10.21
- アリマス特任研究員が「2019年度日本雪氷学会賞(平田賞)」を、青木特任教授が「2019年日本雪氷学会賞(論文賞)」を受賞
- 2019.10.10
- 飛騨帯神岡地域におけるSHRIMP(シュリンプ)ジルコノロジー -日本列島形成史の解明に貢献
- 2019.10.09
- 第16回中高生南極北極科学コンテストの受賞提案を決定
- 2019.09.29
- 南極・北極科学館の来館者が30万人を超えました
- 2019.09.28
- スペイン科学・技術革新・大学省とのMoUを締結
- 2019.09.27
- 北極・ニーオルスンに新たな観測施設を開設しました
- 2019.09.27
- 北極海の海氷面積が9月17日に年間最小値を記録-薄氷化が進行
- 2019.09.06
- アイスランドのグンナルソン北極担当大使、三好外務省北極担当大使が極地研を訪問
- 2019.08.28
- 硫黄同位体組成が解き明かす南極硫酸エアロゾルの起源 -氷期に海洋生物起源の硫酸エアロゾルが減少した新証拠を発見
- 2019.08.26
- 「南極移動基地ユニット」の実証実験の実施について
- 2019.08.26
- 南極の海洋生物起源の硫酸塩エアロゾルは氷期に減少していた ―南極ドームふじアイスコア分析データの解析から
- 2019.08.22
- 幻のコケ「ナンジャモンジャゴケ」が確認されました
- 2019.08.21
- 極地研が所蔵する写真のデジタルアーカイブを公開しました
- 2019.08.19
- お知らせ 地層「千葉セクション」の審査状況について(2019年8月)-“国際境界模式層断面とポイント”認定に向け、第3段階の審査機関に申請書を提出
- 2019.08.08
- 広報誌「極」18号を発行しました
- 2019.08.08
- ホホジロザメが海中でオットセイを襲う様子をバイオロギングで撮影、記録
- 2019.04.27 - 09.06
- 第16回中高生南極北極科学コンテスト(2019年9月6日必着)
- 2019.08.03
- 極地研一般公開「極地研探検2019」
- 2019.06.14
- 太陽系初期における原始惑星の巨大衝突 -隕石の超高精度年代測定が解き明かす小惑星ベスタの謎-
- 2019.06.10
- 地圏研究グループ 竹原真美特任研究員らの論文が昨年に続きIsland Arc誌のTop20ダウンロードに
- 2019.06.05
- 元極地研で南極観測隊員の原圭一郎氏が日本気象学会賞を受賞
- 2019.05.29
- フリオ・フィオル駐日チリ大使が極地研を訪問
- 2019.05.26
- 片岡龍峰准教授による絵本『オーロラみつけた』が出版されました
- 2019.05.21
- 1958年に日本で見られた扇型オーロラの実態を解明
- 2019.05.16
- 渡邉興亞・元所長がJpGUフェローに選ばれました
- 2019.05.14
- 南極隕石ラボラトリーで普通コンドライトの新たな分類決定手法を開発
- 2019.05.10
- 海洋堆積物コアから解明された最終氷期における短期間の氷床変動
- 2019.03.29
- 石川県小松市との科学館連携協定を締結
- 2019.03.26
- 北極陸域から発生するダストが雲での氷晶形成を誘発する
- 2019.03.20
- 生物圏研究グループのJean-Baptiste Thiebot特任研究員がPacific Seabird Group Annual Meeting で発表賞を受賞
- 2019.03.12
- タスマニア州のホッジマン首相が極地研を訪問
- 2019.03.07
- ホホジロザメは待ち伏せ型のハンター
- 2019.02.27
- 愛知県小牧市に落下した隕石の分類を確定「小牧隕石」として国際隕石学会に登録されました
- 2019.02.25
- 秋田県にかほ市との包括連携協定を締結
- 2019.02.21
- 生物圏研究グループの渡辺佑基准教授が執筆した書籍『進化の法則は北極のサメが知っていた』が出版されます
- 2019.02.20
- 2019年度 欧州非干渉散乱(EISCAT)レーダー観測及びデータ解析共同利用の募集について
- 2019.02.08
- オーロラが爆発するとヴァン・アレン帯の電子が上空65kmにまで侵入する
- 2019.01.24
- 教員南極派遣プログラム派遣教員の生田依子教諭(奈良県立青翔中学校・高等学校)が文部科学大臣優秀教職員表彰を受けました
- 2019.01.22
- 近藤豊特任教授らが翻訳した書籍『詳解 大気放射学』が出版されました
- 2019.01.17
- 世界初!地球近傍の宇宙で発生するプラズマと電磁波の相互作用発生域の可視化に成功 ~最新の科学衛星「あらせ」と極北のオーロラ観測から宇宙の物理現象を理解~
- 2019.01.16
- 世界最北の有人島で菌類の新種を発見
- 2019.01.16
- 村山雅美名誉教授のご遺族から南極点到達の顕彰状などが寄贈されました
- 2019.01.15
- 駐日ベラルーシ共和国特命全権大使のルスラン・イエシン博士が南極・北極科学館を見学されました
- 2019.01.09
- 学術誌『Polar Science』でインドの極域科学を特集
- 2018.12.25
- 第62次、第63次南極地域観測隊で実施する一般研究観測、萌芽研究観測を募集します
- 2018.12.25
- 第61次南極地域観測隊で実施する公開利用研究を募集します
- 2018.12.19
- 成蹊学園との包括的連携協定を締結
- 2018.12.06
- 高緯度北極の海鳥営巣崖下の斜面は窒素循環のホットスポット
- 2018.12.04~12.07
- 第9回極域科学シンポジウムのウェブサイトをオープン
- 2018.11.29
- 北極から南極へ気候変動が伝わる2つの経路 ~南極アイスコアのデータから立証~
- 2018.11.19
- お知らせ 地層「千葉セクション」の審査状況について ~GSSP認定へ向けて~
- 2018.11.09
- 11月9日(金)、2018年度北極域研究推進プロジェクト公開講演会『北極の環境変化と人々への影響』を開催します(於:一橋講堂)
- 2018.10.24
- 河野外務大臣が「北極サークル」会議において我が国の北極政策とArCSプロジェクトの取組について紹介
- 2018.10.23
- 南極海での船上気象観測で豪州の低気圧予報を改善 ~豪州の観測船と日本のデータ同化による南極予測可能性研究のさきがけ~
- 2018.10.18
- 2018年の「みらい」北極航海特集ページを公開。航海のようすを随時お知らせします
- 2018.10.17
- 南極から授業をしてくれる先生を募集します!―2019年度教員南極派遣プログラム 派遣教員募集―
- 2018.10.17
- 第15回中高生南極北極科学コンテストの受賞提案を決定
- 2018.10.11
- 小惑星の名前に「極地研」!
- 2018.09.25
- 北極海の海氷面積が9月21日に2018年の最小値を記録 ~減少スピードは停滞、回復時期は遅延~
- 2018.08.30
- 北極域の気象観測で台風の進路予報が向上
- 2018.08.28
- 極地研・竹原真美特任研究員らの論文がIsland Arc誌のTop20ダウンロードに
- 2018.08.22
- 極地研・辻雅晴特任研究員が「第2回バイオインダストリー奨励賞」を受賞
- 2018.08.21
- 生態系の“熱帯化”:温帯で海藻藻場からサンゴ群集への置き換わりが進行するメカニズムを世界で初めて解明 -気候変動、海流輸送、海藻食害による説明-
- 2018.08.09
- 北極と南極の雪を赤く染める藻類の地理的分布の解明
- 2018.08.04
- 国立極地研究所一般公開「極地研探検2018」を開催します
- 2018.07.31
- 南極観測シンポジウム2019を開催ー将来のサイエンスの方向性の提案を募集します
- 2018.07.26
- グレートバリアリーフと氷床変動:世界遺産のグレートバリアリーフ掘削試料が明らかにした未知の急激な氷床変化
- 2018.07.24
- お知らせ 国際標準模式地の審査状況について ~地層「千葉セクション」の認定へ向けて~(2018年7月)
- 2018.07.20
- 南極地域観測将来構想(中間報告)を公開しました
- 2018.07.13
- オホーツク海南部で見られる小さなクリオネと大きなクリオネの謎を解明 ~地球温暖化による海洋環境変化に対する生物の応答解明に期待~
- 2018.07.05
- 千葉時代(チバニアン)提案に不可欠な環境変動記録の復元
- 2018.07.04
- 第15回中高生南極北極科学コンテスト 提案の募集を開始!(〆切:9月6日必着)
- 2018.07.03
- 原始太陽系円盤の中心近くで結晶化したシリカを隕石中に世界で初めて発見
- 2018.06.28
- 北極海航路上の海氷厚分布を高精度に予測できる時間スケールを特定 ~北極低気圧の予測精度に大きく依存~
- 2018.06.01
- 南極の山に、白石和行前所長にちなんだ名称がつきました
- 2018.05.22
- 小型水中無人探査機(ROV)による南極湖沼の湖底連続撮影 ~南極の湖底および海氷下の生物分布状況を調査~
- 2018.05.09
- 深海底の緩やかな起伏が表層海流と海面水温前線を生む ~亜寒帯の表層海流と強い海面水温前線をつくり出す新メカニズムを発見~
- 2018.05.08
- 北極域研究推進プロジェクト(ArCS)若手研究者海外派遣事業 第1回追加募集を開始(応募締切:6月13日必着)
- 2018.05.02
- 宙空圏研究グループ片岡龍峰准教授が「2017年度(平成29年度)日本機械学会賞(論文)」を受賞
- 2018.04.27
- 太陽の自転周期が雷の発生に影響している ~江戸時代の日記の分析で判明~
- 2018.04.27
- オーロラ4Dプロジェクトがくずし字の教育コンテンツ「くずし字、いろいろ」を開発!
- 2018.04.24
- 南極隕石1000個の新たな分類結果を公表しました
- 2018.04.18
- 国際北極環境研究センター 杉村 剛 特任研究員が「2017年度日本雪氷学会関東・中部・西日本支部支部賞(活動賞)」を受賞
- 2018.04.12
- 宮岡宏 教授、小濱広美 広報室副室長が「科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞(理解増進部門)」を受賞
- 2018.04.11
- 「第15回南極設営シンポジウム」(2018.6.4開催)の発表テーマを募集
- 2018.04.11
- 平澤威男・元極地研所長がJpGUフェローに選ばれました
- 2018.03.15
- 渡辺佑基准教授が監修『それでもがんばる!どんまいなペンギン図鑑』が出版されました
- 2018.03.09
- 電気通信大学と包括協定を締結
- 2018.03.03
- SCAR(南極研究科学委員会)設立60周年
- 2018.03.01
- 2018年度 欧州非干渉散乱(EISCAT)レーダー観測及びデータ解析共同利用の募集について