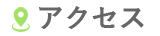調査報告書等
オープンサイエンスのためのデータ管理基盤ハンドブック
国立情報学研究所(NII)では、2022年4月の個人情報保護法改正に焦点を当てたオープンサイエンスのためのデータ管理基盤ハンドブックを作成し、大学等の研究機関に属する研究者をはじめ、企業等民間の研究機関に属する研究者や研究アシスタント、大学事務、さらには研究機関内の研究倫理審査委員会に携わる方等にも有用な内容を提供してきました。
今後は教育・防災・医療における課題整理及びユースケースの紹介も行うなど、より包括的なハンドブックとしていくため、様々な分野の有識者による検討会「デジタル時代のデータ利活用等における法的制度的課題に関する検討会」を情報・システム研究機構(ROIS)に設置し、継続的な改版を行ってまいります。
- オープンサイエンスのためのデータ管理基盤ハンドブック~学術研究者のための“個人情報”の取扱い方について~(第1版)
- オープンサイエンスのためのデータ管理基盤ハンドブック~学術研究者のための“個人情報”の取扱い方について~の概要
お問い合わせ:情報・システム研究機構 本部事務部 企画連携課 研究推進係
handbook[at]rois.ac.jp
※ (at) は @ に置き換えて下さい。
米国における教育のデータ駆動化に関する調査報告書
- 米国における教育のデータ駆動化に関する調査報告書(第三部(1.1版))
※2025年3月31日に1.1版に更新されました
執筆者:情報・システム研究機構 / KDDI総合研究所
国立情報学研究所(NII)では、国内における教育のデータ駆動化に向けた議論をより洗練されたものにすべく、初等・中等教育のデータ駆動化で先行する米国における、教育のデータ駆動化が教育現場にもたらした効果及び教育のデータ駆動化を支える仕組みについて報告してきました。
報告書(第一部(1.2版)、第二部(1.1版))
※第二部は2025年3月31日に1.1版に更新されました
今後は情報・システム研究機構(ROIS)において、社会のデジタル化に関する調査及び報告を行ってまいります。
サマリー
(第1.1版に更新しました)
日本国内では、社会全体のデジタル化に向けた機運が高まっており、教育分野では、2019年に文部科学省が「GIGAスクール構想」による教育のICT化を打ち出し、学習や指導の履歴や成績の推移などのビッグデータを蓄積・分析することで、個々の生徒の学習状況のより深い理解、教育現場の知見の可視化、教育政策への反映などを目指している。
本調査報告書では、第一部、第二部に引き続き、米国および英国におけるコロナ禍の施策効果事例、教育分野における生成AIの影響と活用事例およびトランプ政権発足によるAI規制および教育に関する動向について報告する。
(1)米国はコロナ直後に生徒の成績が数十年前のレベルまで大きく落ち込み、特に人種別では白人・アジア系に比べ黒人・ヒスパニック系の遅れが顕著であった。これに対し、連邦政府は2020年以降支援金を投じ、2022年3月バイデン政権のAmerican Rescue Plan(ARP)等において、教育分野に1,900億ドル(約28.5兆円)の支援金を投入。ARPを活用した学力回復のための施策として、過去の検証で効果が確認されていたHigh-Impact Tutoring(学校のカリキュラムと連動した少人数の個別指導)を推奨。完全オンライン指導を導入したテキサス州や、対面指導を導入したニュージャージー州などで大きな効果を上げている。また教育省は、2023年1月以降Raise the Barという大きな教育目標を掲げ、上記個別指導に加え授業数の増加や教員不足解消などの取り組みを進めデータ追跡を継続している。
(2)英国でも米国同様にコロナ直後に生徒の成績が大きく落ち込み、英国政府は2020年11月以降Recovery Packageにおいて、教育分野に35憶ポンド(約5,005億円)の支援金を投入。その中で経済的に支援が必要な生徒を対象としたNational Tutoring Programme(NTP)などを推進。コロナ前の成績への回復に必要な月数が小学校・中学校で大きく減るなどの効果を上げている。
(3) ChatGPTの登場後、悪影響の可能性を理由に当初利用を禁止した学校や大学が多かったが、懸念事項に留意した上での積極利用の流れとなり、学校現場での活用が進み始めている。また、生成AIの健全な利用のための設計・導入指針となるガイダンスがUNESCOや各国政府・州政府などで策定されている。民間レベルでは、生成AIを活用したツールは既に多くの教育企業が提供し、生徒の個別学習支援(AIチューター)、教員の授業計画/教材作成/評価・フィードバックツールが主流である。2024年2月に実施されたアクセス数ベースの生成AIツール利用実態調査では、Top10の中に教育関連ツールが3件入った。学校がこれらAIツールを導入する際には、生徒の成績向上や教員の作業量削減などの「効果」が重要となる。国家レベルでは、英国教育基金財団(EEF)は2024年7月、教員のChatGPT利用による作業量削減検証を実施し平均で約30%の削減効果を示した。また、米国教育省 教育科学研究所(IES)は、重要課題への生成AI活用において、文章だけでなく、音声・画像・動画などを扱うマルチモーダル機能を強化したAIチューターの開発・実証を推進する4つのU-GAINセンターを設立。英国科学イノベーション技術省(DSIT)は、2023年9月より生成AI学習用データの共有化を推進している。今後は、生徒の成績向上効果も含めた教育現場での有効性を一歩一歩検証・定量評価し、エビデンスの蓄積を進めると同時に、教員にしかできない指導との役割分担を考えることで現状のさまざまな課題解決が期待できる。
(4) 2025年1月20日 アメリカ合衆国 第47代大統領にドナルド・トランプ氏が就任し、前バイデン政権のAI規制に関する大統領令撤廃や教育省の廃止を求める動きを進めており、今後も注視する必要がある。
日本のデジタル防災に向けた米国防災技術・事例に関する調査報告書
- 日本のデジタル防災に向けた米国防災技術・事例に関する調査報告書
執筆者:情報・システム研究機構 / KDDI総合研究所
サマリー
近年、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・頻発化している。これらへの対応は、世界における共通課題であり、他国の取り組みを確認することは、非常に有用である。本調査報告書では、米国における防災対応やシステムついて概観し、特徴的な事例や萌芽的な先進技術の活用動向に着目して可能な限り詳述するとともに、これを支える米国の防災の仕組みについて報告する。
(1)米国の取り組みは、大きく以下の3点にまとめられる。 ①米国防災では、国家準備目標(National Preparedness Goal)を達成するため、Federal Emergency Management Agency(FEMA)をはじめとする連邦政府組織が主導しつつ、災害対応の仕組みやシステムがすべてのフェーズで整備されており、地方・州政府、自治体、民間などの数多くの組織が、Whole-Communityのスローガンの下、それらを活用して災害対応にあたっている②災害データの可視化およびデータプラットフォームについては、官民連携のシステムも多く、防災に資する様々な立場の人材育成に力を入れており、教育・訓練システムが充実している③災害時の初動対応・復旧作業を迅速化するためのセンシング技術も重要な役割を占め、人工衛星、ドローン、IoTの活用事例が積極的に活用されている。
(2) 事前準備~災害対応~振り返りに及ぶ災害の全フェーズにおいて最新技術を取り入れながらデジタル化を実現している。また、連邦政府~地域間や官民の連携によりこの実現に必要な組織、教育・訓練、アプリケーションが充実している。つまり、全フェーズにおいて、組織横断でデジタル化を推進する仕組みが充実している。
(3) 2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震をみても、日本の防災におけるデジタル化は確実に進んでおり、本震災は、日本における大規模災害の初動対応において、低軌道衛星「Starlink」を用いた通信確保や、船上基地局の共同運営、ドローンによる医薬品の輸送が行われた日本における最初のケースとなった。今後、気候変動により災害の激甚化・頻発化が予想される中においては、災害データの利活用が発展することに加え、全フェーズにおいてデータに基づいた防災対策・支援が行われることで、日本のデジタル防災が、世界規模の防災・減災を推進していくことが期待される。